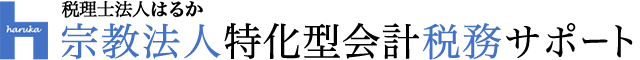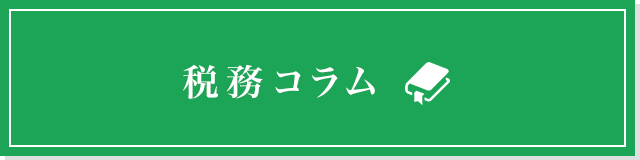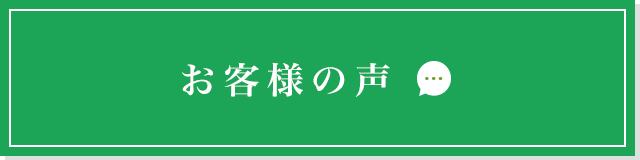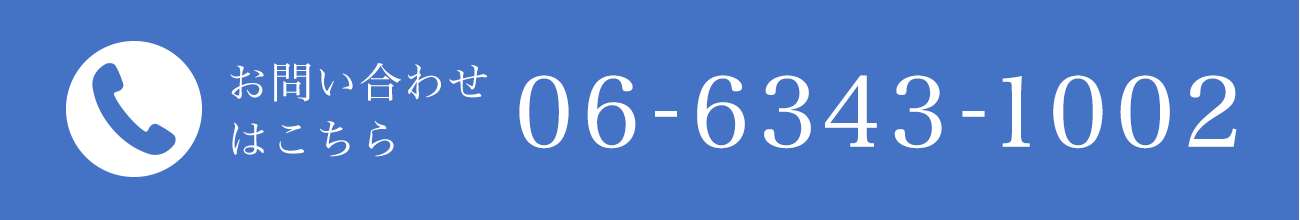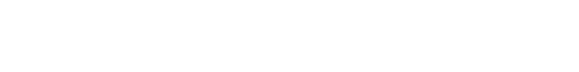宗教法人への寄付・相続Q&A
QA4. 措置法40条の適用される要件等(改訂2025.8.25)
個人が宗教法人に土地などの財産を寄付した場合、寄付した個人は原則として、所得税59
条1項1号の規定によって、時価で譲渡したこととみなされ、所得税の課税対象となりま
す。ただし、措置法40条の適用をうけることができれば、譲渡がなかったものとして、課
税されません。(以上QA2)
では、寄付した個人が措置法40条の申請を行った場合に、どのような要件を満たしてい
れば申請がみとめられるかが措置法施行令25条の17⑤に定められています。
その内容について記載いたします。
措置法40条の適用にあたっては、措置法施行令25条の17⑤において、次の各号を満た
せば、適用されるとされます。
1号:当該贈与が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増
進に著しく寄与すること
2号:贈与を受けた法人で、寄付された財産を寄付のあった日から2年以内にその公益目
的事業の用に直接供するか又は供する見込みであること
3号:この贈与が、贈与者の所得税の負担、贈与者の親族その他特別関係者の相続税(贈
与税)の負担を不当に減少させるものでないこと
各号の具体的基準はさらに以下のようになっています。
下記の「通達」とは「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」
直資2-181(例規)昭和55年4月23日
| 施行令25条の17⑤ | その具体的な考え方や要件 | |||
| 1号 | 当該贈与又は遺贈が、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること。 | 通達12 | (1) 公益目的事業の規模 | 公益目的事業が、その事業の内容に応じ、その公益目的事業を行う地域又は分野において社会的存在として認識される程度の規模を有すること。 |
| (2) 公益の分配 | 公益を必要とするすべての者(やむを得ない場合においてはこれらの者から公平に選出された者)に与えられるなど公益の分配が適正に行われること。 | |||
| (3) 事業の営利性 | その公益の対価がその事業の遂行に直接必要な経費と比べて過大でないことその他当該公益目的事業の運営が営利企業的に行われている事実がないこと。 | |||
| (4) 法令の遵守等 | 事業の運営につき、法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。 | |||
| 2号 | 当該贈与又は遺贈に係る財産又は法第40条第1項に規定する代替資産が、当該贈与又は遺贈があつた日から2年を経過する日までの期間(同項に規定する期間をいう。)内に、当該公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであること | 通達13 | (公益目的事業の用に直接供される) 原則として、当該財産等そのものが、当該贈与又は遺贈を受けた公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供されるかどうかにより行うことに留意する。 ただし、株式、著作権などのようにその財産の性質上その財産を公益目的事業の用に直接供することができないものである場合には、各年の配当金、印税収入などその財産から生ずる果実の全部が当該公益目的事業の用に供されるかどうかにより、当該財産が当該公益目的事業の用に直接供されるかどうかを判定して差し支えないものとして取り扱う。 | |
| 通達14 | (福利厚生施設) 財産等が、贈与又は遺贈を受けた公益法人等の理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下「役員等」という。)若しくは当該公益法人等の社員又は職員のための宿舎、保養所その他の福利厚生施設として利用される場合には、当該財産等は、公益目的事業の用に直接供されていることとはならないことに留意する。 | |||
| 通達15 | (2年を経過する日までの期間内に公益目的事業の用に直接供される見込みであるかどうかの判定) 当該財産等が、当該贈与又は遺贈があった日から2年を経過する日までの期間内に、当該公益法人等の当該贈与又は遺贈に係る公益目的事業の用に直接供されることについて、例えば、建物の設計図、資金計画などその具体的計画があり、かつ、その計画の実現性があるかどうかにより行うものとする。 | |||
| 3号 | 当該贈与若しくは遺贈をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させ、又は当該贈与若しくは遺贈をした者の親族その他これらの者と相続税法第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること。
| 施行令25条の17⑥ 下記の各号の要検を満たすときは、不当に減少させる結果とならないと認められる | ||
| 1号 | その運営組織が適正である(これはQA5に記載)とともに、規則において、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(役員等)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(親族等)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも3分の1以下とする旨の定めがあること。 | |||
| 2号 | 財産の贈与若しくは遺贈をする者、公益法人等の役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。 | |||
| 3号 | 規則において、その公益法人等が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。 | |||
| 4号 | その公益法人等につき公益に反する事実がないこと。 | |||
| 5号 | 公益法人等が当該贈与又は遺贈により株式の取得をした場合には、当該取得により当該公益法人等の有することとなる当該株式の発行法人の株式がその発行済株式の総数の2分の1を超えることとならないこと。 | |||
通達17 下記の2要件を満たしている場合は、上記の2号から第5号までの要件を満たしているときは、負担を不当に減少させる結果とならないと認められるものとして取り扱う。
| ||||